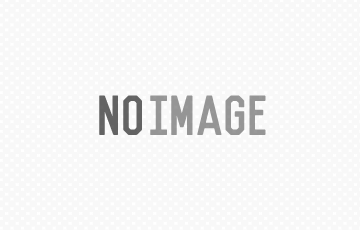今日は「株は、常に生き残ることを最優先すべし」について考えた。
今日は「株は、常に生き残ることを最優先すべし」について考えた。
※10年ぶりの下落相場にどう対応する(まとめ)
(前回コラムの続きから)
新年、明けましておめでとうございます(*^_^*)
今年は何かと、チャレンジ速度を上げていきたいと思います。
そんな新年の抱負は、、、、またの機会にして、
まずは直近株コラムのまとめです。
でないと、後出しジャンケンになりそうな雰囲気。
というのも、前回の株価予想が、
現実味を帯びてきそうな雰囲気だから。
現在、先物で日経平均は14000円台に突入。
これは、かなり、やばい流れです。
先物とは、日経平均の数ヶ月先を予測する、
いわば花札ゲームみたいなものですが、
とうぜん、先物が大きく下がれば、
現在株価もその予想につれて、下がることが多いです。
さらに、ドル円も105円を軽く割ってしまいました。
日本市場が休みの間に、
かなり多くの仕掛けがされてしまいました。
売りの勢力、強いですねー。
ここから、買いの軍勢はかなり苦しいです。
だいぶ、覚悟が必要かも。
この2つの現象だけでも、下がる要素が大きいのです。
が、それにつれて、海外投資勢力の、
タイミングが合わせたような連鎖売りがはじまっているから。
その金額、うん兆円。
売りを急いでいるという事は、つまり、どういうことでしょう。
海外ヘッジファンドはポジションをゼロ、
現金というニュートラルにすることはしません(成績が悪くなれば、顧客を失います)、
とうぜん、日本株へのポジションは、1つです。
おそらく、カラ売りポジション。
カラ売りが強まれば、さらに株価は下がります。
ヘッジ勢は、狙っています。
ロスカットや追証になり、投資家が資産を放り出すのを。
損失の逆回転が回るほど、
ヘッジファンドというのは、儲かる仕組みなのです。
それが、カラ売りポジションの戦略的な仕掛け、つまり「(リスク)ヘッジ」なわけです。
それを金やオイルなどの資源ファンドを巻き込んで戦略的に行うから、ヘッジするファンド。
つまり、ヘッジファンドです。
そうなれば、この先、手を緩めないでしょう。
15000円を抜けると、
さらに多くの追証が発生します。
そうすると、システム損失の限界で、機関投資家もポジションを減らします。
すると、全投資家が全銘柄を投げます。
でないと、
信用保証率を担保できない事態になります。
すると、13000円が見えてきます。
これが、セリングクライマックスです。
ヘッジ勢は、ここまでわかっています。
さらに、国際的な貿易摩擦や景気の悪化シグナルなどが広がっていますので。
もちろん、ぼくの予想は当たらないのが通例です。
今回も、当たらないかも。。。
そう、当たらないから、ここまで「最悪」の先にある、
「まさか」を予想して、いくつもの戦略オプションを練るわけですね。
(おわり)
Source: PR会社でナンバーワンを目指す!上岡正明オフィシャルブログ